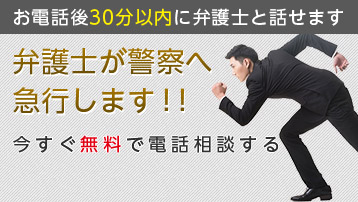飲酒(酒気帯び)運転で逮捕! 勾留期間や罰則、裁判の流れ
- 交通事故・交通違反
- 飲酒運転

警察庁が公表している令和5年の犯罪統計によると、令和5年に大阪府内において飲酒運転で検挙された件数は1039件でした。この数字は、全国で4番目に多い数字ですので、大阪府では飲酒運転の違反件数が多いことがわかります。
飲酒運転によって取り締まりを受けると、刑事罰と行政処分、両方の罪に問われる可能性があります。この記事では、飲酒運転と酒気帯び運転で問われうる罪、逮捕された場合の手続きや量刑について、堺オフィスの弁護士が解説します。


1、飲酒運転で問われる罪
-
(1)2種類の飲酒運転│酒気帯び・酒酔いの違い
飲酒運転で問われる可能性のある罪には、以下の2種類があります。
- 酒気帯び運転:アルコールの保有量で判断されます。
- 酒酔い運転:アルコールの影響による運動能力の低下で判断されます。
具体的には、酒気帯び運転は「呼気1Lあたり0.15mg以上」または「血液1mLあたり0.3mg以上」のアルコールを保有している状態で車両等を運転した場合に処罰対象となります。
他方、酒酔い運転は、アルコールの影響で正常な運転ができない状態で車両等を運転した場合をいいます。酒気帯び運転とは違い、酒酔い運転かどうかの判断には数値による基準は設けられておらず、運転者の状態や行動などから総合的に判断されます。
なお、処罰対象かどうかの基準値を下回っていたとしても、体内に少しでもアルコールが残っている状態で車両等を運転することは酒気帯び運転として法律により禁じられていますが、本コラムでは、わかりやすさの観点から、罰則や行政処分の対象となるものを「酒気帯び運転」としています。
また、飲酒運転が発覚した後の対応によっては、以下のような罪に問われる可能性もあります。運転手が問われうる罪- 呼気アルコール検査を拒否した罪
- 緊急措置義務違反
- 報告義務違反
- 過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)
- 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
- 危険運転致死傷罪
- 同乗者の幇助罪
- 車両提供罪
- 酒類提供罪
- 同乗罪
-
(2)身体からアルコールが抜けるまでの時間は?
体重60kgの標準的な成人男性が4時間で分解できる飲酒量の目安は以下のとおりです。
アルコール分解時間4時間に対する、飲酒量目安- ビール(500ml)アルコール度数5%
- チューハイ(350ml)アルコール度数7%
- 日本酒(180ml)アルコール度数15%
- ワイン(200ml)アルコール度数12%
ただし、これはあくまでも目安ですので、実際のアルコールの耐性は、個人の体質によって異なります。
「お酒に強いから、これくらいの飲酒で酔わないはず」と思っていても、実際には体内のアルコール濃度が基準値を超えていることもありますし、その状態で運転すれば酒気帯び運転として処罰される可能性があります。
少量のお酒で酔ってしまう体質であれば体内のアルコール濃度は基準値を下回っていたとしても、正常な運転ができないおそれがあるとして、酒酔い運転として処罰される場合がありえます。
このようにアルコール分解能力には個人差がありますので、自分の体質や体調を考え、適度な飲酒量を心がけましょう。
また、そもそも体内に少しでもアルコールが残っている状態での運転は酒気帯び運転として法律により禁じられていますので、運転する予定がある場合には飲酒を控え、飲酒してしまった場合には運転をしないことが大切です。 -
(3)飲酒運転が厳罰化された背景
道路交通法が施行された昭和35年、飲酒運転は違反行為ではありましたが罰則は設けられていませんでした。しかし、悪質な飲酒運転による事故などをきっかけとして社会的な批判が高まり、厳罰化が進みました。
特に平成19年の飲酒運転厳罰化、平成21年の行政処分強化は、平成18年8月に幼児3人が亡くなった飲酒運転による悲惨な事故が少なからず影響していると考えられます。
2、飲酒運転の逮捕・勾留で生じる罰
-
(1)2種類の量刑│刑事罰と行政処分
飲酒運転で逮捕されて有罪になると、刑事罰と免許関連の行政刑罰の両方が生じます。
刑事罰- 酒酔い運転:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
行政処分(※前歴及びその他の累積点数がない場合)- 酒酔い運転:免許取り消し、欠格期間3年
- 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上の場合):免許取り消しと欠格期間2年
- 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.15mg~0.25mg/Lの場合):90日の免許停止
-
(2)飲酒運転による事故の量刑は重い
飲酒運転によって事故を起こしてしまった場合、量刑はさらに重くなります。
たとえば、人身事故の場合、自動車運転過失運転致死傷罪として罪を問われる可能性があります。自動車運転過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の拘禁刑または禁錮もしくは100万円以下の罰金です。
また、悪質な運転によって事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪として罪に問われる可能性があります。危険運転致死傷罪の法定刑は、傷害を負わせた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑です。
さらに、飲酒運転をして死傷者がでる事故を起こした際に、飲酒の発覚を隠そうとすると、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に問われる可能性があります。過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は、12年以下の拘禁刑です。
なお、飲酒運転の発覚をおそれ、酔いをさましてから出頭しても、隠蔽(いんぺい)しようとしたことが発覚すると、より重い刑罰が科せられる可能性があります。
お問い合わせください。
3、飲酒運転をしてしまった場合、後日逮捕される可能性はある?
軽い気持ちで飲酒運転をしてしまったけれど、特に何も問題は起こさずに帰宅できた場合、逮捕される可能性はあるのでしょうか。
飲酒運転は、アルコールが身体の中にある、もしくはアルコールの影響により正常な運転ができない状態という証拠が必要となるため、現行犯逮捕される場合がほとんどです。しかし、飲酒運転中に事故を起こしたなどの記録が残っているような場合は、飲酒運転をした後日逮捕されるケースもあります。
お問い合わせください。
4、逮捕・勾留・裁判の流れ
酒気帯び運転または酒酔い運転で逮捕された後の流れは、以下のとおりです。
-
(1)逮捕
飲酒検問や職務質問により酒気帯び運転または酒酔い運転が発覚すると、その場で現行犯逮捕になるケースが多いです。逮捕されると、そのまま警察署に連行され、警察官による取り調べを受けます。
逮捕による身体拘束には時間制限が設けられていて、警察は48時間以内に事件を検察官に送致するか、釈放するかの判断をしなければなりません。 -
(2)勾留
検察官は、取り調べを行い、身体拘束を継続するかどうかを検討します。検察官が引き続き身体拘束を行う必要があると判断した場合は、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求をしなければなりません。
勾留請求があると勾留の裁判が行われ、裁判官は、勾留質問を行い、勾留を許可するかどうかを判断します。勾留が許可されると原則として10日間、その後さらに延長されると最長20日間の身体拘束となります。
なお、身体拘束の必要がないと判断されると釈放されます。 -
(3)起訴〜刑事裁判
検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
検察官により起訴されると、公開の法廷で刑事裁判が行われ、裁判官から判決が言い渡されますが、酒気帯び運転または酒酔い運転の罪については、検察官により書面審理のみで罰金等の刑罰を求める略式での起訴がなされ、公開の法廷での裁判は行われないものの、罰金刑が言い渡されるケースが多いです。
このように起訴されて有罪判決が確定したり、略式起訴の形で罰金が言い渡されたりすると前科が付く一方、不起訴になれば前科が付くことはありません。
お問い合わせください。
5、飲酒運転について弁護士に相談するメリット
飲酒運転をしてしまったときは、弁護士に相談すると以下のようなメリットがありますので、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)勾留を回避して早期釈放を目指せる
飲酒運転により逮捕・勾留されてしまうと、長期間の身体拘束を受けることになります。
特に、勾留による身体拘束期間は、最長で20日間にも及びますので、逮捕されてしまったときは勾留を阻止することが重要になります。しかし、逮捕されてから勾留を決定する裁判までの時間は、最長で72時間しかなく、実際は逮捕の翌日にはすでに勾留の裁判となっているケースも多いです。
また、逮捕された場合、少なくとも勾留の裁判が終わるまで、弁護士以外は面会をすることができません。
早期に弁護士に依頼することで、捜査機関や裁判官に対して、勾留の裁判の前に勾留の必要性がないことを伝えることができ、勾留を回避できる可能性が高くなります。 -
(2)不起訴処分獲得に向けたサポートが受けられる
酒気帯び運転または酒酔い運転の罪で起訴されて、有罪判決が確定したり、略式起訴の形で罰金が言い渡されたりすると前科が付くため、社会生活に影響がでるおそれがあります。
弁護士は不起訴処分獲得に向けてサポートを行い、前科を回避するためにさまざまな弁護活動を行います。なお、飲酒運転が明らかであれば、早期に事実関係を認めて、反省の態度を示すことも重要です。 -
(3)有利な判決獲得に向けた弁護活動を行ってくれる
酒気帯び運転または酒酔い運転の罪で起訴されてしまった場合でも、弁護士は有利な判決獲得に向けた弁護活動を行いますので、拘禁刑を回避して罰金刑を獲得する、執行猶予付き判決を獲得する、拘禁刑の刑期を短縮するなどの効果が期待できます。
刑事事件はスピード勝負といわれるように迅速な対応が重要になります。そのため、飲酒運転により逮捕されてしまったときは早期に弁護士に相談することをおすすめします。
お問い合わせください。
6、まとめ
飲酒運転は、酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類に分けることができ、態様と量刑が異なります。運転する予定があれば飲酒を控える、飲酒したら運転は避けるなど、飲酒運転をしないことが大事ですが、万が一飲酒運転をしてしまった場合、飲酒運転を隠そうとするとさらに罪状が重くなってしまう可能性が高いため、呼気検査は適切に受け、事故は正直に申告するようにしましょう。
飲酒運転によって逮捕されてしまうかもしれない、すでに警察の取り調べを受けているなど不安を抱えている方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでは、実績のある弁護士が解決に向けて迅速な対応を行います。お困りの際は、まずはご相談ください。
お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています