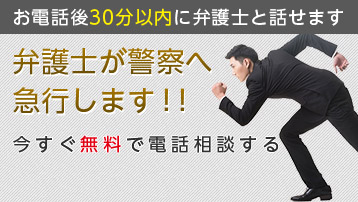強要罪とは│逮捕の成立要件や事例(土下座・謝罪文・脅迫等)
- その他
- 強要罪とは

強要罪とは、他人に暴行や脅迫などを行い、義務のないことを行わせる犯罪です。
脅迫罪よりも罪は重く、身近な問題から発展しやすい犯罪であることが特徴です。
本コラムでは、強要罪の成立要件や逮捕されたあとの流れ、弁護士に依頼すべき理由についてベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。


1、強要罪とは?
強要罪の成立要件や脅迫罪との違いなどについて解説します。
-
(1)強要罪の成立要件
強要罪は以下のいずれかによって、人に「義務のないことを行わせ」、または「権利の行使を妨害した」場合に成立します(刑法第223条)。
強要罪の成立要件
- 被害者本人の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加える旨を告知して「脅迫」した
- 被害者の親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加える旨を告知して脅迫した
- 「暴行」を用いた
「義務のないことを行わせる」とは、土下座を強要したり、無理やり働かせたりする行為が該当します。
「権利の行使を妨害する」とは、お金を返すように求める権利(債権)を行使させないようにしたり、株主総会に出席しないよう強要したりする行為が該当します。
また、「脅迫」「暴行」の具体例は以下のものが挙げられます。- 脅迫の具体例:「殺すぞ」「悪評を流すぞ」「クビにするぞ」などと言って脅す
- 暴行の具体例:殴る・蹴る・物を投げるなどの行為
-
(2)脅迫罪との違い
強要罪と似た犯罪として、脅迫罪があります。相手を脅すという点では同じですが、どこに違いがあるのでしょうか。
- 脅迫罪とは:「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が罰せられる犯罪。誰かに対し危害を与えるような内容を告知し、相手が畏怖すれば成立する。
- 強要罪とは:脅迫行為に畏怖するだけでは足りず、なんらかの強要行為が必要。
強要罪は、「義務のないことを行わせる」ための脅迫行為が必要です。ここが、脅迫罪と強要罪の大きな違いとなります。
また、脅迫罪と強要罪では、罪の重さも変わります。前述した通り、強要罪は3年以下の懲役が課される可能性がありますが、脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
強要罪と比べて脅迫罪は、懲役刑が1年短いこと、罰金刑があるといった違いがあります。
このように、同じような罪に思える脅迫罪と強要罪ですが、「義務のないことを命令したのか」どうかで、罪の重さが大きく変わります。 -
(3)恐喝罪との違い
強要罪と同様に、相手に義務のない行為をさせる犯罪として「恐喝罪」(刑法第249条)が挙げられます。
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた場合、または財産上不法の利益を得た場合、もしくは他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」とされており、強要罪よりも重くなっています。
「恐喝」とは、財物または財産上の利益を交付させるために、暴行または脅迫によって被害者を畏怖させることをいいます。
「財物」や「財産上の利益」を得ることを目的としているのが、恐喝罪の大きな特徴です。 -
(4)強要罪の事例│土下座・謝罪文の強要・脅迫・暴行
強要罪の事例を見てみましょう。
たとえば、お店の店員に「土下座しろ」などと義務のないことを強要するケースがあります。商品の不備などクレームが発展して、犯罪になってしまうのです。過度なクレームは、相手に恐怖心を植え付け、エスカレートすることにより、相手に必要のないことを強要してしまうことになるので、強要罪となります。
「謝罪文を書かせる」ときにも、場合によっては強要罪が適用されます。
また、暴行や脅迫を加えた上で契約書などにサインさせる行為も強要罪となります。いわゆる「押し売り」事例ですが、暴行や脅迫を用いて、相手を畏怖させた上で無理やり購入させると、強要罪に当てはまります。
殴る蹴るなどの強い暴行ではなくとも、「無理やり腕をつかむ」「相手に向かって物を投げる」などの行動も暴行として判断される可能性があるでしょう。
このように、強要罪は、身近なトラブルに潜んでいることが多い犯罪です。
2、逮捕・勾留・起訴・裁判の流れ
強要罪で逮捕されてしまった後の流れについて解説します。
-
(1)逮捕|最大72時間
強要罪の疑いで逮捕されると、最大48時間にわたって警察官が身柄を拘束します。警察官は48時間以内に、被疑者を釈放するかどうか判断します。
警察官が身柄拘束を続けるべきと判断した場合、被疑者の身柄は検察官へ送致されます。検察官は24時間以内に、裁判官に対して被疑者の勾留を請求するかどうかを判断します。
最初に身柄を拘束されてから、勾留請求または釈放がなされるまでが逮捕の期間です。逮捕の期間は72時間以内としなければなりません。
逮捕期間中は、警察官や検察官の取調べを受けます。家族の面会は認められず、面会できるのは弁護人(弁護士)のみです。 -
(2)勾留|最大20日間
検察官の勾留請求を受けた裁判官は、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められると判断したときは、勾留状を発します。
勾留状が発せられると、被疑者の身柄拘束が逮捕から勾留へと移行します。
起訴前の勾留期間は、当初は10日間までですが、さらに最大10日間の延長が認められています。したがって、起訴前の勾留期間は最大20日間、逮捕と通算すると最大23日間です。
逮捕から勾留に移行すると、原則として家族の面会が認められるようになります。ただし、接見禁止処分が行われている場合は、引き続き家族の面会は認められません。 -
(3)起訴
原則として勾留期間が満了するまでに、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断します。
不起訴の場合は、被疑者はその時点で釈放されます。
これに対して起訴された場合は、勾留が続くことになります。また、被疑者の呼称が「被告人」へと変わります。
起訴後の勾留期間は当初2か月間で、その後は1か月ごとに更新可能です。裁判所に対して保釈を請求して認められれば、保釈保証金を預けることを条件として、一時的に身柄が解放されます。 -
(4)刑事裁判
起訴されてから1か月程度が経過した段階で、裁判所の法廷において刑事裁判(公判手続き)が行われます。刑事裁判は、検察官が犯罪事実を立証し、被告人側が反論する形で進行します。
犯罪要件がすべて認められる場合に限り、裁判所は有罪判決を言い渡します。犯罪要件がわずかでも欠けている場合には、裁判所は無罪判決を言い渡します。
その後、控訴や上告を経て判決が確定し、有罪判決が確定したときは刑が執行されます。
ただし、3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑に限り、刑の執行が猶予されることがあります。
お問い合わせください。
3、強要罪における起訴・実刑の可能性
強要罪で起訴される確率や実刑を受ける確率がどの程度あるのか解説します。
-
(1)起訴される可能性は4割程度
令和5年(2023)年の検察庁の統計資料(被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員、起訴率の累年比較)によると、強要罪のみの起訴率のデータはないものの、強要罪を含めた脅迫罪の起訴率は、33.2%となっています。
前年は34.6%となっているため、起訴率自体は、減少傾向にあるといえます。
出典:「政府統計の総合窓口」(e-Stat)
この統計によると、脅迫罪、強要罪の3割以上は起訴される可能性があるということがわかります。不起訴は約7割ですが、事件の態様によっては起訴される確率が十分にあるということも理解しておくべきでしょう。
また、社会的影響が大きい場合や、行為態様が重いというケースでは、起訴される可能性が上がります。 -
(2)実刑になる可能性はそう高くない
強要罪の場合、多くのケースで執行猶予付きの有罪判決となります。執行猶予がつくと、執行猶予期間中に新たに罪を重ねることや執行猶予の条件に反することがなければ、そのまま今の社会生活を送ることができます。
もっとも、他の犯罪ですでに執行猶予を受けている場合には、実刑を受ける可能性が高くなります。 -
(3)強要罪の時効は3年間
強要罪の加害者は、罪の意識がないケースがありますし、すぐには逮捕されないケースも多いです。このような事例の場合、強要罪の時効について知っておくべきです。
強要罪の時効は、3年間です。この間に、被害者が警察に告訴するようなことがあれば、いつでも逮捕される可能性があります。
被害者は脅迫や暴行行為で、恐怖した状態となっています。その場では、加害者に従い黙っていたかもしれませんが、後日勇気を出して警察に被害届を出す可能性も十分にあります。その場で警察が来なくとも、あとで問題になることは多々ありますので、理解しておきましょう。
このように、強要罪には時効がありますが、その場で警察にバレなかったからといって、安心できる状況ではありません。
4、強要罪で逮捕されたら早急に弁護士に依頼すべき理由
弁護士に依頼すべき理由と弁護活動の内容を解説します。
-
(1)重要なことは、48時間以内に弁護士に依頼すること
一番重要なことは、できるだけ早く弁護士に依頼することです。具体的には、逮捕後48時間以内に弁護士に連絡をすることが肝心です。
検察に送致されてしまうと、勾留請求まで24時間しか残されておらず、この間だけで勾留請求を回避することは難しくなるからです。勾留請求を回避すると早期釈放につながるため、勾留請求前に、弁護士に依頼することが重要になるのです。
これ以外にも、早い段階で依頼することにより、示談交渉がスムーズになります。遅くとも検察官による処分決定までに示談をまとめることで、不起訴の判断の可能性を高めることができます。
強要罪で逮捕されてしまった場合には、起訴の可能性も十分にあります。そのため、できるだけ早い段階で弁護活動を開始することが大切です。 -
(2)弁護活動の内容とは?
弁護士に依頼した後は、以下のように弁護活動が進みます。
- ① 弁護士から事件について助言を受ける
- ② 示談交渉を早期に開始する
- ③ 勾留を回避するための弁護活動
- ④ 不起訴を目指す弁護活動
- ⑤ 減刑を求める弁護活動
ひとつずつ解説していきます。
① 弁護士から事件について助言を受ける
弁護士に依頼すると、接見などの際に取調べの対処方法など、アドバイスを受けることができます。逮捕されたときは動揺されている方も多いものですが、弁護士が接見することで、取調べに対する不安なども話すことができ、さまざまな相談をすることもできます。
② 示談交渉を早期に開始する
依頼を受けたあとは、担当弁護士は被害者との示談交渉を開始します。示談は起訴・不起訴の判断に大きく影響するので非常に重要です。
真摯に謝罪をした上で、示談金の支払いなどをまとめていくことになります。被害者から許しを得た場合には、不起訴の可能性も高くなるでしょう。
逮捕されている場合、示談交渉を自分で行うことは難しいですし、家族から示談交渉を行ってもらおうとしても、被害者が拒絶することが多いです。第三者かつ法律のプロである弁護士に任せる方がスムーズに進むため、示談成立には弁護士への依頼が重要です。
③ 勾留を回避するための弁護活動
勾留前の場合は、「勾留を回避するための弁護活動」も行い、早期釈放を目指します。勾留に十分な理由がないことなどを検察官に主張していくことで、勾留請求を回避できる可能性があります。
④ 不起訴を目指す弁護活動
不起訴になれば、そこで事件は終息するため、裁判や実刑になることはありません。ここまでに示談がまとまっていれば、不起訴の確率も高くなります。
⑤ 減刑を求める弁護活動
起訴されてしまった場合には、「減刑を求める弁護活動」を行います。たとえば、依頼者が十分な反省をしていることを裁判官に理解してもらえるように、謝罪文や、今後は家族がしっかり監督していく等記した誓約書などを提示していくことになります。
これ以外にも、当該事件における個別的な事情にまで踏み込んで弁護方針を作成していくことで、量刑が軽くなるように弁護活動を行っていきます。
お問い合わせください。
5、まとめ
強要罪で逮捕された場合は、起訴されて有罪判決を受けるおそれがあります。執行猶予が付く可能性は高いものの、前科が残ってしまいます。また、再犯の場合や余罪がある場合は、実刑判決を受ける可能性も否定できません。
重い刑事処分を避けるためには、早期に弁護士へ相談することが大切です。
まだご自身が逮捕されていないなら、逮捕される前に弁護士へ相談しましょう。また、家族が強要罪の疑いで逮捕されてしまった場合も、速やかに弁護士相談することをおすすめします。
他人に対して強要をしてしまった方や、家族が強要罪の疑いで逮捕された方は、まずはベリーベスト法律事務所 堺オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています