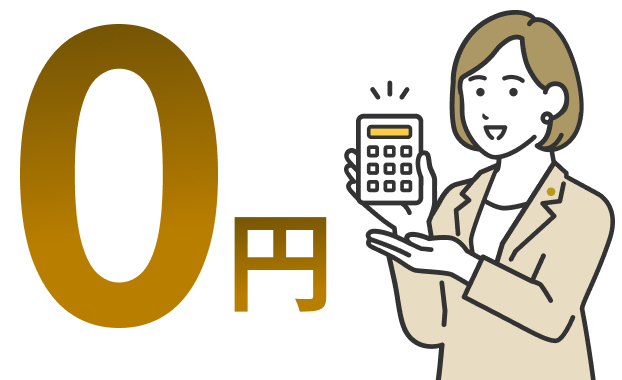愛人とその子どもに相続権はある? 堺オフィスの弁護士が解説します
- 遺産を受け取る方
- 愛人
- 相続

堺市内で相続問題が起きて、調停や裁判を行うときは大阪地方・家庭裁判所堺支部か、大阪地方・家庭裁判所で申し立てることになるでしょう。司法統計によると、平成29年中に大阪地方・家庭裁判所を舞台に遺産分割問題で争った事件の総数は810件でした。
亡くなったご家族に愛人やその子どもが存在することを知ったら、驚かれることでしょう。しかし、そのような感情に悩まされているばかりではいられません。なぜなら、その愛人や子どもが亡くなったご家族の財産を相続する権利を主張してくること、あるいはすでに権利を有していることが考えられるからです。
もし、そのような事態に直面した場合、ご遺族は財産の相続に関するご自身の権利を守るために適切な行動をとる必要があります。その際にお役に立つことを目的に、本コンテンツでは財産の相続について亡くなった家族の愛人やその子どもが持つ権利、あるいは亡くなったご家族が生前に愛人やその子どもに対して有利な取り計らいをしていた場合にとるべき対処法についてご紹介します。
1、原則として愛人は相続人になれない
-
(1)配偶者と愛人、内縁の妻とは?
最初に、配偶者と愛人および内縁の妻の違いについて確認しておきましょう。
配偶者とは、役所に婚姻届を提出して民法上の婚姻関係にある異性をいいます。これに対して、そのような婚姻関係になく恋愛関係にある異性を愛人といい、法的な婚姻関係はないが、同居して生計を一にしており、事実婚の状態にある女性を内縁の妻と称することが一般的です。
ある者が相続人になることができるか否かは、この法的な婚姻関係の有無により大きく左右されます。 -
(2)愛人は法定相続人ではない
民法では、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を有する「法定相続人」の範囲を定めています。具体的には、相続発生時において被相続人の配偶者・子どもまたは孫・親・兄弟姉妹が法定相続人と定義されており、民法上の婚姻関係にある配偶者は原則として法定相続人とされます。その一方で、被相続人の配偶者でもなければ血縁関係もない愛人や内縁の妻は法定相続人とされていないのです。
なお、被相続人に法定相続人が誰もいない場合、原則として、誰も相続することができません。ただし、例外として、被相続人と生計を同じくしていた者や、身の回りの世話を献身的に努めていた者がいた場合、これらの者の請求によって、「特別縁故者」として被相続人の遺産の一部または全部を相続する権利が認められる場合があります。
内縁の妻と異なり、基本的に被相続人と同居していないことを前提としている愛人が特別縁故者として認められる可能性は極めて低いでしょう。
2、愛人でも財産を相続ができる場合がある
前述のとおり、愛人が法定相続人になることはありません。しかし、それはあくまで被相続人の財産は法定相続人が相続するという原則論においてのことです。仮に、被相続人が愛人に財産を贈与するように生前にしかるべき手だてを講じていた場合は、愛人でも被相続人の財産を取得できます。
-
(1)遺言
被相続人が遺言により指定した相続人や相続割合は、被相続人の遺志を尊重する民法の考え方から強い法的効力を持ちます。したがって、被相続人が亡くなった後に遺産分割協議(遺産をどのように分けるか相続人間で話し合うこと)などの場で法定相続人が遺言の内容に反対したとしても、基本的に被相続人の遺志である遺言書の記載通りに遺産を分割することになるでしょう。しかし、満場一致で遺言書の記載通りに分割しない方法で合意したときはこの限りではありません。
-
(2)死因贈与契約
死因贈与契約とは、財産を遺す被相続人(贈与者)と財産を受け取る愛人(受贈者)が、被相続人の生前にお互いの合意のもと、贈与者である被相続人の死亡時に財産が受贈者である愛人へ贈与されることを取り決める契約です。契約ですので、愛人が自ら撤回しない限りは原則として有効となります。
3、愛人の子どもには相続権があるの?
相続権がない愛人の子どもについても、親である愛人と同様に法定相続人と認められていません。仮に愛人の子どもが被相続人と実の親子と同じように良好な関係を築いていたとしても、これは覆らないのです。
なぜなら、民法は配偶者のほかに被相続人と血のつながりがある直系の血族しか法定相続人になることができないと規定しているためです。同様に、義理の親や義理の兄弟姉妹などとよばれる人たちに法定相続割合が認められていません。
したがって、被相続人の配偶者ではない愛人の子どもは被相続人の血族ではないため相続権は認められていないのです。しかし、例外があります。その例外について知っておきましょう。
-
(1)認知
実子のうち、法的な婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子どもを「嫡出子」といいます。これに対して、婚姻関係にない男女の間で生まれた子どもは「非嫡出子」といいます。
もし被相続人が生前に愛人の子どもを認知していた場合、その子どもには被相続人と愛人が婚姻関係になくても被相続人と法律上の親子関係が認められるようになります。その結果、相続においては愛人の子どもに嫡出子と同等の相続権が発生するのです。 -
(2)養子縁組
血縁関係のない子どもと、戸籍法などに定められた諸手続を踏むことで親子関係を生じせしめることを養子縁組といいます。被相続人が生前に養子縁組を行っていた子どもには、認知されていた場合と同様に相続権が発生します。なお、民法には養子の数に制限規定がありません。
4、「愛人に全財産を遺贈/贈与する」という遺言や死因贈与契約が出てきたときの対処法
このような内容の遺言または死因贈与契約が出てきた場合でも、愛人に全財産が渡ってしまうと失望する必要はありません。愛人やその子どもからすべての財産を確保することは難しいかもしれませんが、まずは冷静に対処してください。
-
(1)遺言または死因贈与契約の内容を確認する
法定相続人が被相続人と特段の問題のない関係であったのにも拘らず、遺言または死因贈与契約の内容や目的が愛人との不貞関係を維持するためなど明らかに公序良俗や倫理に反している場合は、家庭裁判所への訴えにより遺言または死因贈与契約そのものの無効が認められる可能性があります。
-
(2)遺留分減殺請求をする
配偶者や実子などの法定相続人がいるのにも拘らず、愛人という特定の人に「全財産を遺贈/贈与する」としている時点で、その遺言または死因贈与契約は他の相続人の遺留分を侵害しています。
遺留分とは、被相続人の遺志やその他の状況によらず、法定相続人に対して民法が保証する最低限の取り分です。法定相続人が最低限の財産を相続する権利でもあります(ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません)。
遺言や死因贈与契約により遺留分を侵害された法定相続人は、遺言や死因贈与契約の内容に関係なく遺留分を侵害した人、つまり愛人に対し侵害された遺留分相当の支払いを請求する「遺留分減殺請求(改正民法施行後は遺留分侵害額請求)」を行う権利を有します。これに愛人が応じない場合は家庭裁判所で遺留分減殺調停、さらには遺留分減殺請求訴訟を提起することになります。
万が一、和解ないし判決により愛人に対して遺留分侵害相当額の支払いが確定しても愛人が支払いに応じない場合は、強制力のある民事執行の手続きをとることになります。なお、被相続人の相続が発生し、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年を経過すると遺留分減殺請求は認められません。ご注意ください。
5、ひとりで悩まず、弁護士に相談しよう
相続は難解な各種法律や制度を踏まえた手続きを要します。場合によっては財産の配分をめぐり相続人間の心情や利害が反発し合うことになるためさまざまなトラブルが生じやすいものです。特に財産の配分について被相続人の愛人が当事者にいると、なおさらでしょう。
このような場合は、弁護士と相談しながら交渉や相続手続を進めることを強くおすすめします。相続問題の解決に実績のある弁護士であれば、経験に裏付けられた適切なアドバイスが期待できます。さらには、あなたの代理人として愛人など利害関係者との交渉や遺留分侵害請求などの法的な諸手続なども交渉することも可能です。
あなたやご家族の権利を守るために、悩まれたときは弁護士に相談してください。
6、まとめ
相続は一生のうちで多くても数回程度しか経験しない出来事です。ましてや亡くなったご家族に愛人がいて財産を相続する権利を主張してくるような場面に遭うことは何回もないでしょう。つまり、当事者としてこのような事例に十分な経験を積む必要はありません。
大切なことはひとりで悩まないことです。だからこそ弁護士のように経験を積んだ専門家の知見を得ながら対処することが重要なポイントなのです。ベリーベスト法律事務所 堺オフィスでもアドバイスを行います。掛かる不測の事態が生じたとしても円満な相続ができることを願ってやみません。
ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています